夏目漱石といえば、「吾輩は猫である」「坊ちゃん」など数々の文学作品を残したことで知られる明治時代の小説家です。
作品は中学校や高校の国語の教科書にも採用されているので、夏目漱石の名前を知っていたり、読んだりしたことがある方も多いと思います。
しかし、夏目漱石がどのような人物でどのような功績があるのかまで詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか?
この記事では、夏目漱石について分かりやすく解説します。
スポンサーリンク
天才の略歴

1867年(1歳) 東京都に生まれる
1868年(2歳) 父の知人である塩原昌之介の養子となる
1876年(10歳) 養父母の離婚によって夏目家に戻る
1879年(13歳) 第一中学校正則科に入学
1884年(18歳) 大学予備校に入学
1890年(24歳) 帝国大学英文科に入学
1893年(27歳) 帝国大学卒業、教師になる
1895年(29歳) 愛媛県尋常中学校(現在の松山東高校)に赴任
1900年(34歳) イギリス留学
1905年(39歳) 雑誌「ホトトギス」で「吾輩は猫である」を発表
1907年(41歳) 東京朝日新聞に入社、職業作家となる
1910年(44歳) 胃潰瘍を患い、伊豆・修善寺で意識不明になる
1916年(50歳) 胃潰瘍再発のため死去
スポンサーリンク
遅咲きの頑固者
夏目漱石は現代であればノーベル文学賞を受賞していたといわれるほどの、日本を代表する小説家と評価されています。
しかし、意外とデビューは遅く、38歳のときに「吾輩は猫である」を発表。
たくさんの作品を残していますが、小説家として活動したのは実質10年ほどでした。
ちなみに、「夏目」は本名ですが「漱石」はペンネームで、本名は金之助といいます。
漱石という名は中国の故事「漱石枕流(そうせきちんりゅう)」が由来。
もともとは夏目漱石と交流があった俳人・正岡子規が使っていたペンネームのひとつで、意味は負け惜しみが強いこと、変わり者のたとえです。
この名の通り、生徒に「先生の言っていることは辞書と意味が違う」と指摘されたとき、「辞書の方が間違っているから直しておきなさい」と言い放ったというエピソードもあります。
スポンサーリンク
夏目漱石の代表作は?
作家としては遅咲きの夏目漱石ですが、教科書にも採用されて馴染みのある作品がたくさんあります。
一部をご紹介します。
吾輩は猫である
「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」という書き出しで始まるこの小説は猫が主人公で、猫の視点を通して人間のやり取りを上手く書き出しています。
あまりにも有名な作品ですが、これが漱石のデビュー作です。
坊ちゃん
夏目漱石が教師となり、愛媛県の学校に赴任したときの実体験をもとに書かれた作品。
東京から松山へ赴任した「坊ちゃん」が松山で出会った個性豊かな同僚教師と繰り広げるコミカルなやり取りが見どころ。人間描写の豊かさから中学校の国語教科書にも掲載されているので、読んだ方も多いのでは。
こころ
主人公の「私」は「先生」と出会って交流を持ちますが、「先生」は友人の「K」と妻との壮絶な三角関係の過去があり、その行く末を書いた遺書を「私」に残して自殺を図ります。
日本の文学作品でトップの売り上げを誇る、漱石の代表作。
スポンサーリンク
千円札の肖像にもなった

夏目漱石といえば、千円札の肖像をイメージする方もいるのでは。
日本を代表する小説家で、明治時代以降に活躍し、特徴的なヒゲがあるので、お札の肖像に選ばれる基準を満たしています。
夏目漱石は1984年から2007年まで20年以上も千円札の肖像に採用され、現在もごく少数ですが流通しています。もちろん、普通に千円札として使えます。
2024年には千円札が現在の野口英世から北里柴三郎の肖像に変わるので、もし手元に夏目漱石の千円札をお持ちなら記念に取っておいてもいいかもしれません。
スポンサーリンク
繊細だった漱石

夏目漱石の教え子には藤村操がいました。
日光の華厳の滝で「巌頭之感(がんとうのかん)」を書き残し、入水自殺を図ったことで有名なエリート学生です。
漱石が第一高等学校に赴任したばかりの頃、授業態度が悪い藤村操に注意したことがありました。
その2日後に自殺したことからかなりのショックを受け、「漱石が藤村を自殺に追い込んだ」とまで言われました。実際は自殺の原因は別にあります。
この出来事は作品の中でも
「打ちゃっておくと巌頭の吟でも書いて華厳滝から飛び込むかも知れない。(吾輩は猫である)」
「余の視るところにては、かの青年は美の一字のために、捨つべからざる命を捨てたるものと思う。(草枕)」
などと触れているほど、影響が大きかったようです。
スポンサーリンク
闘病続きの人生だった

実は、夏目漱石は若い頃から「神経衰弱(現代でいうところのうつ病)」を患っていて、被害妄想や空虚感に悩まされていたようです。
1903年にイギリス留学から帰国すると、小泉八雲の後任として日本人で初めて第一高等学校や東京帝国大学(現在の東京大学)の講師に就任しています。
しかし、夏目漱石の文学論は学生から人気がなく授業をボイコットされることもあり、立て続けに兄たちを亡くすなどの心労も重なって神経衰弱になったとされます。
それ以外にも幼少期には天然痘にかかり、17歳で虫垂炎、19歳で腹膜炎、糖尿病や胃潰瘍などさまざまな病気を経験。
晩年は健康だった時期のほうが少ないほどで、「病気のデパート」という異名もあります。
1年の半分以上入院していた時期もあり、夏目漱石の小説は病気の合間に執筆されました。
多くの作品を残しましたが、執筆活動をしていたのは10年ほどです。
デビュー作「吾輩は猫である」は俳人・高浜虚子(たかはまきょし)が神経衰弱で苦しむ夏目漱石に小説を書いて気を紛らわすことをすすめたことで誕生しました。
このとき、夏目漱石を救ったのが1匹の黒猫で、「吾輩は猫である」はリアルな物語です。
いつの間にか家にすみついた野良猫を通して自分を客観的に見ることができ、神経衰弱に苦しむ夏目漱石の心を癒してくれました。
猫は漱石一家にかわいがられていましたが、最期まで名前がなく、ずっと「猫」と呼ばれていたそうです。
スポンサーリンク
夏目漱石、天才の理由まとめ
夏目漱石は江戸時代の終わりに生まれ、明治維新や日本の近代化の激動を見て育ちました。
子供の頃から優秀でしたが非常に神経質で、ややストレス耐性が低かったようです。
草枕の冒頭の一節には「智に働けば角が立つ。状に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。」とあります。
これは、“すべての人が理屈を通すか、情に厚いか、意地っ張りかに分類されるとしたら、どのタイプも生きづらい”という意味です。
夏目漱石の作品には、このような生きづらさを抱える人や人生に悩む人のヒントになる言葉がたくさんあります。
漱石自身が繊細で生きづらさを抱えていたからこそ、100年たっても親しまれる作品を残すことができたのかもしれませんね。
スポンサーリンク
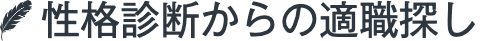

夏目漱石より女の子が大好きです!!!